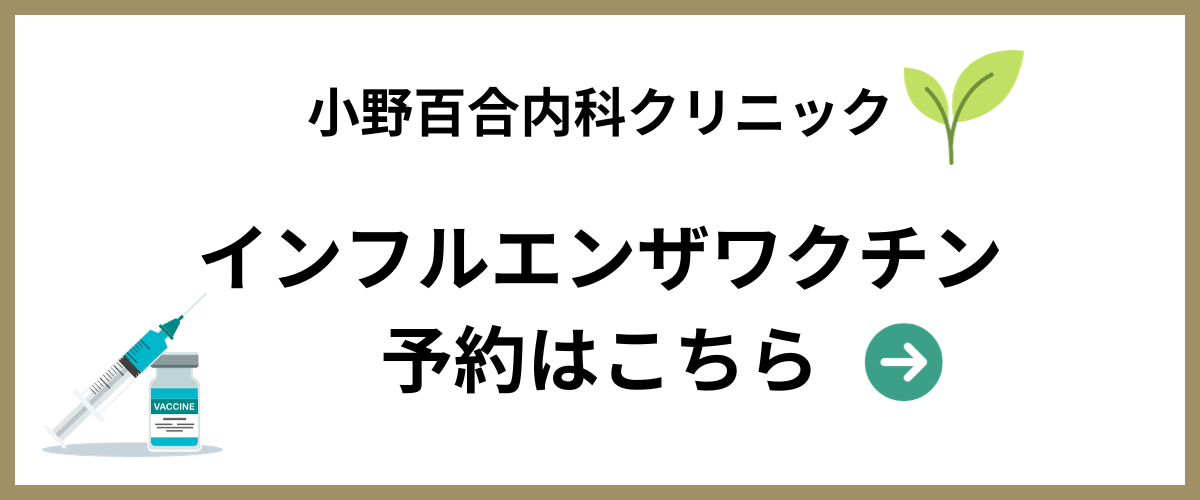札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。脂質と聞くと「油っこい食べ物」「体に悪いもの」というイメージを持つ方も少なくないと思います。しかし、脂質は糖質・たんぱく質と並ぶ三大栄養素のひとつであり、生命を維持するために欠かせない存在です。その主成分である「脂肪酸」は、エネルギー源として利用されるだけでなく、細胞膜やホルモンの材料にもなります。また、皮下脂肪として外部から体を守り、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収を助けるなど、多彩な役割を担っています。今回はそんな脂肪酸について内科医の目線から解説してみようと思います。このブログを読んでみなさんも脂肪酸について詳しくなれれば幸いです。
 脂肪酸とは?過剰摂取には注意が必要
脂肪酸とは?過剰摂取には注意が必要
飽和脂肪酸は、化学的に二重結合を持たず安定した構造をしています。そのため常温で固体となることが多く、肉の脂身やバター、チーズ、ラードなどに豊富に含まれます。
しかし、飽和脂肪酸を摂りすぎると血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増加し、動脈硬化や心筋梗塞などの循環器疾患のリスクが高まることが分かっています。実際に厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」でも、飽和脂肪酸の摂取量は総エネルギー量の7%以下に抑えることが推奨されています。
豚バラ肉や牛リブロース、乳製品のクリームなどは飽和脂肪酸の含有量が特に多く、100g食べただけで1日の目標量を超えてしまうこともあります。そのため「摂りすぎない」ことが大切です。
不飽和脂肪酸の基本と種類
一方で、不飽和脂肪酸は分子内に二重結合を持ち、常温で液体の油に多く含まれます。血液中のLDLコレステロールや中性脂肪を低下させる働きがあり、健康に良い油として注目されています。
不飽和脂肪酸には2つの種類があります。
-
一価不飽和脂肪酸(二重結合が1つ):代表はオレイン酸。オリーブオイルやなたね油、アボカドに豊富で、酸化に強く加熱調理にも適しています。
-
多価不飽和脂肪酸(二重結合が2つ以上):さらにn-6系(オメガ6)とn-3系(オメガ3)に分類されます。
n-6系脂肪酸(オメガ6)
ごま油、大豆油、コーン油などに多いリノール酸や、レバーに含まれるアラキドン酸が代表的です。体内で作れないため必須脂肪酸と呼ばれますが、摂りすぎると炎症を促進し、HDL(善玉)コレステロールを下げる可能性があります。
n-3系脂肪酸(オメガ3)
アマニ油やエゴマ油に含まれるα-リノレン酸、青魚に豊富なEPAやDHAが代表です。こちらも必須脂肪酸で、心筋梗塞や脳卒中リスクの低下、中性脂肪の改善など多くの健康効果が期待されています。ただし熱に弱く酸化しやすいため、加熱せずに使うのがポイントです。
動物性脂肪と植物性脂肪の違い
脂質の種類を「動物性」と「植物性」で比較すると、違いがはっきり見えてきます。
-
動物性脂肪:飽和脂肪酸が多く含まれ、肉類や乳製品に豊富。風味やコクを生みますが、過剰摂取でコレステロール値が上がるリスクがあります。
-
植物性脂肪:オリーブオイル、ナッツ類、アボカドなどに多く含まれ、不飽和脂肪酸が中心。コレステロール改善や血管保護の効果が期待できます。
両者を「どちらか一方だけに偏る」のではなく、量とバランスを意識して取り入れることが大切です。
バランスの良い脂質摂取のコツ
脂質は「種類」と「量」の両方に注意して摂ることが重要です。いくら健康に良いとされる油でも、1gあたり9kcalと高エネルギーであることに変わりはなく、摂りすぎは肥満や生活習慣病のリスクとなります。
実践的な工夫としては、
-
バターをオリーブオイルに置き換える
-
サラダにアマニ油をかける
-
青魚(サンマ、サバ、イワシ)を週に2回以上食べる
などがあります。
また、日常的に摂りやすい植物油の多くはオメガ6脂肪酸なので、意識してオメガ3を増やす工夫が必要です。ヨーグルトや味噌汁に小さじ1杯のアマニ油を加えるだけでも、毎日の摂取量を改善できます。

まとめ
-
飽和脂肪酸は取りすぎると心疾患のリスクを高めるため摂取量を控えることが大切。
-
不飽和脂肪酸は体に良い働きを持ち、特にオメガ3脂肪酸の積極的な摂取が推奨される。
-
動物性脂肪と植物性脂肪の特徴を理解し、バランスよく取り入れることが健康維持のカギ。
脂質は「悪者」ではなく、正しく選び、適量を守れば私たちの体を支える大切な栄養素です。今日から油の使い方を少し工夫して、健康的な食生活を実践してみましょう。
いかがだったでしょうか。また次のブログでお会いしましょう。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック
院長 小野渉