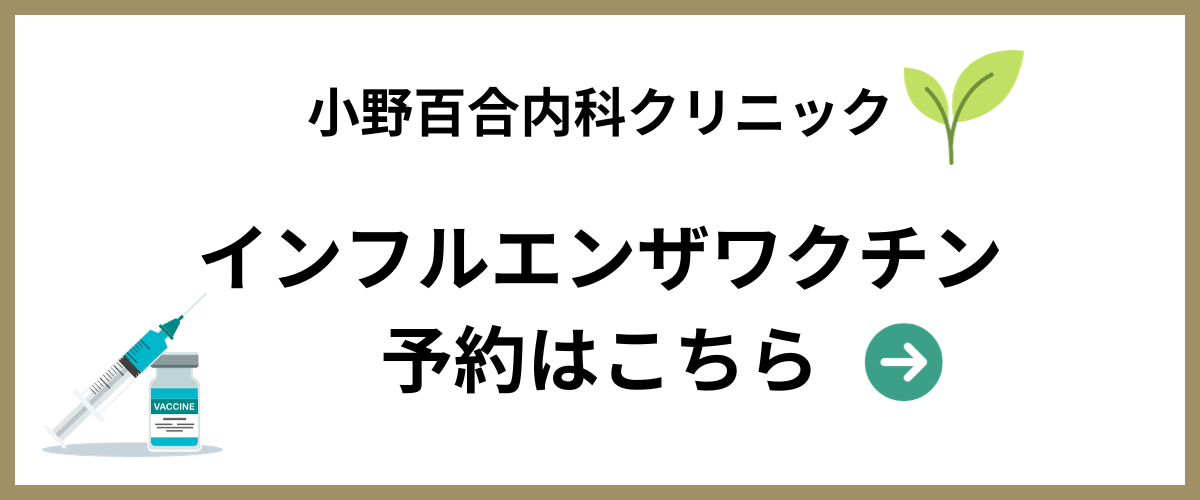札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。秋は果物が特に美味しい季節で、食卓に色鮮やかな果物が並ぶと心も体も満たされます。しかし「果物は糖分が多いから糖尿病の人は控えなければならないのでは」と不安に感じる方も多くいます。結論としては、果物は正しく量を守り、種類や食べ方を工夫すれば、糖尿病や肥満の管理をしている人にとっても十分に健康的に取り入れられる食品です。果物にはビタミンやミネラル、食物繊維、さらにカロテノイドやポリフェノールといった抗酸化成分が含まれており、血管や細胞を守る役割を果たします。ただし、ブドウ糖や果糖、ショ糖といった糖質も豊富に含まれているため、食べ過ぎるとHbA1cの上昇、中性脂肪の増加、体重増加につながり、糖尿病と肥満の悪循環を招くことがあります。したがって、果物は“禁止”ではなく“賢くコントロールする”食品と理解することが重要です。

目次
果物が持つ栄養素とその健康効果
果物の色を彩るカロテノイドには、代表的なβ-カロテンやリコピンがあり、これらは体内の活性酸素を取り除く働きをします。活性酸素は血管の老化や動脈硬化の原因になるため、抗酸化作用を持つ果物を日常的に食べることは健康寿命の延伸に直結します。また、ブドウやベリー類に含まれるポリフェノールの一種であるアントシアニンも、血糖コントロールや心血管疾患予防に関わることが報告されています。さらに、食物繊維は血糖値の急激な上昇を防ぎ、便秘予防やコレステロール低下に寄与します。糖尿病の人にとって果物は「糖質のリスク」と「抗酸化や整腸のメリット」が共存する食材であり、食事療法の中で上手に位置づけることが大切です。

皮ごと食べるメリットとジュースの落とし穴
近年の研究では、果物を皮や芯まで含めて食べている人は、そうでない人に比べて糖尿病の発症リスクが低いことが示されています。果物の皮にはフロリジンなどの機能性成分や食物繊維が豊富に含まれており、インスリンの感受性改善や血糖上昇抑制に寄与します。その一方で、果物をジュースにすると食物繊維が失われ、吸収スピードが速まり、血糖値が急上昇するリスクが高まります。さらにジュースは飲みやすいため摂取量が増えやすく、100%果汁であってもHbA1cの悪化につながることがあります。果物は「食べるもの」であり、「飲むもの」ではないという意識を持つことが、食事療法における大切なポイントです。
ドライフルーツは便利だが注意が必要
携帯に便利で保存性が高いドライフルーツは、間食として健康的に利用できる食品と評価されています。栄養素が凝縮されているため、ビタミンや食物繊維を効率よく摂取でき、BMIや血圧が低い傾向にあるとの研究結果もあります。ただし、乾燥させることで糖分も濃縮されるため、少量でも糖質を多く含みます。さらに砂糖やシロップが加えられている商品では血糖値の急上昇を招きかねません。したがって、選ぶ際には無加糖でシンプルな製品を選び、摂取量を少量に抑えることが肝要です。ドライフルーツは生の果物の代替ではなく、補助的に取り入れるものとして考えるのが賢明です。
果物の摂取目安とおすすめの種類
果物の摂取量については、糖尿病の患者さんでは1日100g以内、あるいは食品交換表に基づいた1単位(約80kcal)が目安とされています。例えば、リンゴなら中サイズの半分、バナナは中1本、みかんは小2個程度が適量です。糖質が比較的少なく血糖値を上げにくい果物には、イチゴ、ブルーベリー、ラズベリー、グレープフルーツ、オレンジ、ナシ、アンズなどがあります。逆に、バナナ、桃、柿、ブドウなどは糖質が高めであるため、量をしっかり守ることが重要です。さらに、食べる時間は活動量が多い朝から昼に設定し、夕食後のデザートとしては控えると血糖値管理に有利です。
血糖を上げにくくする実践的な食べ方
果物を安全に楽しむためにはいくつかの工夫があります。まず、食後のデザートとしてヨーグルトやナッツと一緒に食べると、タンパク質や脂質、食物繊維が糖の吸収を緩やかにしてくれます。また、果物は一度にまとめて食べるより、小分けにして摂取する方が血糖スパイクを防ぎやすいです。さらに、リブレなどの持続血糖測定器を活用すれば、自分に合う種類や量を把握しやすくなります。重要なのは、果物を完全に避けるのではなく「どの種類を、どのくらい、いつ食べるか」を設計し、自分のHbA1cや体重、中性脂肪の数値と照らし合わせて管理することです。
まとめ:果物は“我慢”ではなく“設計して楽しむ”食材
糖尿病や肥満の管理において、果物を全面的に禁止する必要はありません。むしろ適量を守り、種類や食べ方を工夫すれば、果物の栄養や抗酸化作用を取り入れながら生活の質を高めることができます。大切なのは、果物を「正しく設計して取り入れる」という姿勢です。食事療法の一環として果物を楽しみ、自己管理の指標であるHbA1cなどの検査結果を定期的に確認しながら、自分に合った食生活を続けていきましょう。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック
院長 小野渉