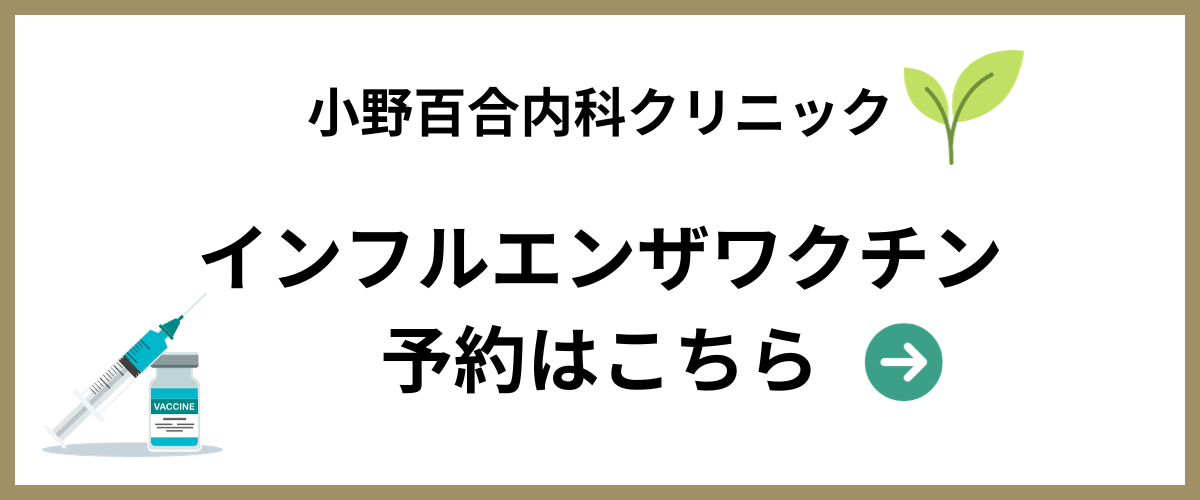札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。糖尿病と聞くと「太っている人がなる病気」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし実際には、糖尿病の進行により「食べても痩せる」「急に体重が減少する」といった現象が起こることがあります。これは体の代謝やホルモンの働きが大きく関わっている重要なサインです。本記事では、糖尿病で体重が減ってしまう理由や注意すべき症状、さらには治療方法について糖尿病内科医の目線から詳しく解説します。
目次
糖尿病で痩せるメカニズム
健康な人では、食事で摂取したブドウ糖が膵臓から分泌されるインスリンの働きによって細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。しかし糖尿病では、インスリンが不足したり効きにくくなったりするため、食べた糖をうまく利用できません。すると体はエネルギー不足を補うために、脂肪や筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとします。その結果、食欲があって食べているのに体重が減少していくのです。とくに1型糖尿病では数週間で数キロ単位の急激な体重減少が見られることもあり、注意が必要です。
糖尿病以外で痩せる病気
体重減少は必ずしも糖尿病だけに限りません。代表的な原因としては以下が挙げられます。
-
甲状腺機能亢進症(バセドウ病):代謝が異常に高まり、食べても痩せる
-
悪性腫瘍(がん):がん細胞に栄養が奪われ、体重が落ちる
-
慢性消耗性疾患(心不全・COPDなど)
-
感染症(結核、HIVなど)
-
うつ病や認知症による食欲低下
このように、体重減少の背景にはさまざまな病気が隠れているため、原因を自己判断せず医師に相談することが重要です。
インスリンは「太るために必要なホルモン」
意外に思われるかもしれませんが、インスリンは「太るために欠かせないホルモン」です。インスリンがしっかり働くと、血液中の糖が脂肪組織に取り込まれ、体はエネルギーを蓄えることができます。逆に、インスリンの分泌量が少ない人は血糖値が下がらず、脂肪もつきにくいため「痩せ型糖尿病」と呼ばれる状態になります。したがって「太らない=健康」とは限らず、痩せている糖尿病患者さんはむしろ治療が難しいケースもあるのです。
痩せている糖尿病患者さんの治療
糖尿病の基本治療は食事療法・運動療法・薬物療法の3本柱ですが、痩せている患者さんの場合は食事制限を強めるとさらに体重が落ちてしまうため、食事療法はあえて制限しないことが多いです。治療の中心は薬物療法であり、膵臓のインスリン分泌が乏しい場合にはインスリン注射が必要になるケースもあります。糖質制限ダイエットは痩せ型糖尿病には不向きで、免疫力や筋肉量をさらに低下させてしまうリスクがあるため注意が必要です。

糖尿病治療で太ることもある?
一方で、インスリン注射やGLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬など治療薬の影響で体重が増えたり減ったりすることもあります。インスリン注射を始めると、今まで利用できなかった糖が細胞に取り込まれるため、体重が増加することもあります。これは悪いことではなく、血糖値の改善に伴う自然な変化であり、食事や運動の工夫でコントロールしていくことが大切です。
急な体重減少は受診のサイン
もし「食べても痩せる」「ここ数か月で急に体重が落ちた」という場合、糖尿病や他の重大な病気が隠れている可能性があります。特に次の症状があるときは早めの受診をおすすめします。
-
異常なのどの渇き
-
尿の回数や量が増える
-
だるさや疲れやすさ
-
視力の低下、手足のしびれ
医学的には半年で体重の5%以上減少した場合、病的な体重減少とされます。自己判断せずに医師の診察を受けることが大切です。
まとめ
糖尿病で痩せるのは「体が糖を利用できず、脂肪や筋肉を分解してしまうため」です。痩せ型糖尿病は治療が難しく、食事制限よりも薬物療法が中心となります。さらに、体重減少は糖尿病だけでなく、甲状腺疾患やがんなどの重大な病気が原因のこともあります。もし意図せず痩せてきている場合は、早めに医療機関を受診し、正しい診断と治療を受けることが健康を守る第一歩です。
いかがだったでしょうか。
また次のブログでお会いしましょう
小野百合内科クリニック
院長 小野渉