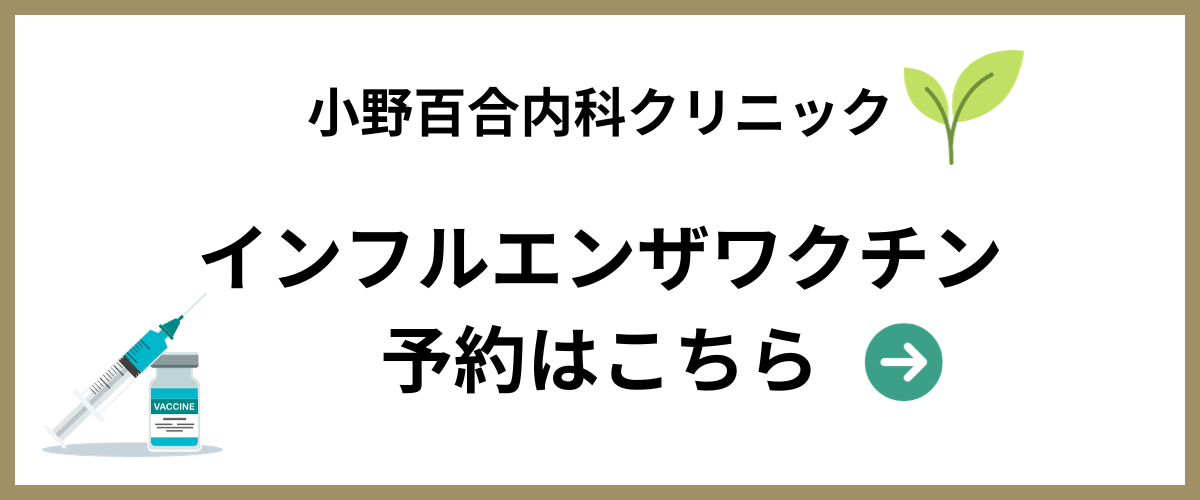こんにちは。札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。今回は、「麻疹(はしか)」という非常に感染力の強い疾患の潜伏期間について、内科医の目線から詳しくお話ししていきます。麻疹はウイルス性の急性疾患で、特効薬がなく、ときに生命の危険をもたらすこともあるため、正しい知識を身につけることが非常に大切です。このブログを読んで麻疹についての知識を深めていただければ幸いです。
目次
麻疹(はしか)とはどのような病気か
麻疹は「麻しんウイルス」によって引き起こされる感染症です。一般には「はしか」と呼ばれ、古くから子どもの間で流行する代表的な疾患として知られてきました。しかし、現在では大人も含めて注意が必要な病気です。主な症状には以下のようなものがあります。
- 発熱(38℃~39℃以上)
- 咳・鼻水・くしゃみなど、いわゆるかぜ症状
- 結膜炎症状(目の充血や目やに、光をまぶしく感じる羞明など)
- 口の中の粘膜にできる白い斑点(コプリック斑)
- 全身に及ぶ赤い発疹(顔面から出始め、徐々に全身へ広がる)
また、肺炎や中耳炎、クループ、脳炎などの重い合併症を引き起こすこともあるため、軽視できない感染症です。特に免疫力の弱い乳幼児や基礎疾患のある方、妊婦さんなどでは重症化しやすく、命にかかわるケースもあります。

麻疹の“潜伏期間”とは
潜伏期間の定義
潜伏期間とは、ウイルスに感染してから初期症状が現れるまでの期間を指します。麻疹においては、一般的に10~12日程度が目安とされていますが、文献や症例によっては7~21日ほどの幅があると報告されています。感染が成立した時期や患者さんの免疫状態によっても、実際の潜伏期間には多少の差が生じます。
一般的に言われる潜伏期間の“ずれ”の理由
- ワクチン接種歴
過去に麻疹ワクチンを1回のみ接種していた方や、母親からの移行抗体がまだ少し残っている赤ちゃんなどは、ウイルスへの抵抗力が「完全ではないが、まったくゼロでもない」状態になりやすいとされています。そのため、感染しても症状発現までに通常より時間がかかったり、逆に少し短くなったりする場合があります。 - 個々人の免疫力の差
年齢、基礎疾患の有無、栄養状態などが複合的に影響して、潜伏期間にばらつきが生じることがあります。
このように、麻疹の潜伏期間は「○日」と一律に断定しにくい面があるのですが、「7~21日」程度の幅を念頭に置き、特に10~12日という数字がよく目安として用いられます。
潜伏期間が長いことで生じるリスク
潜伏期間がある程度長いということは、以下のようなリスクにつながります。
- 感染拡大の原因になりやすい
病院や学校、保育園、職場などで感染者が出た場合、「潜伏期の人」が周囲に気づかれないまま日常生活を送ってしまう可能性があります。麻疹は非常に感染力が強く、空気感染まで起こすため、わずかな接触でもあっという間に広がります。 - 流行をコントロールしにくい
麻疹の感染が疑われた際、何日目から周囲に感染力が出るのかを把握することが難しく、初期対応が遅れる恐れがあります。
一般的には、麻疹は症状(特に発疹)が出る3~5日前から発疹が消えて4日後くらいまで感染力があると言われています。患者さん本人も「まだ自分はかぜ程度だろう」と軽く考えて外出するうちに、ウイルスを拡散してしまう場合があるのです。 - 診断の遅れ
かぜ症状とよく似ているため、「まさか麻疹だとは思わなかった」というケースも少なくありません。特に潜伏期間が長めの場合、感染源との接触から10日以上たって発症することもあるため、感染したタイミングとの結びつきがわかりにくく、医療機関への受診が遅れてしまうリスクがあります。
修飾麻疹と潜伏期間の関係
修飾麻疹とは?
ワクチン接種によってある程度の免疫を持っているものの、完全には十分でない人が感染することで、軽症あるいは典型的でない形ではしかを発症する場合があります。これを「修飾麻疹」と呼びます。
- 高熱があまり出ない、または出ても短期間
- 発疹が部分的にしか出ない
- コプリック斑が見られない
潜伏期間の延長
修飾麻疹では潜伏期間が通常よりも長引くことがあるのが特徴です。そのため、本人や周囲が麻疹とは気づかずに普通のかぜや軽い発疹性疾患と誤認してしまい、知らないうちに感染源としてウイルスを広げてしまう可能性があります。
潜伏期間中の行動・注意点
麻疹に感染しているかどうかは、潜伏期間中に明確に判断することは難しいですが、以下の点を意識しておくとリスクを下げられます。
- 麻疹の流行状況や接触歴を把握する
近年は新型コロナウイルス流行の影響で、海外や国内で小児の定期接種率が下がっていると指摘されています。その結果、免疫を持たない人が増加し、はしかの患者が散発的に発生しています。もし周囲で麻疹の発症があったり、渡航歴のある人と接触があった場合には、数日~2週間程度は自身の健康状態に注意しましょう。 - 発熱やかぜ症状が出たら早めに受診する
発熱(特に38℃以上が継続)、咳・鼻水、結膜炎症状、口腔内のコプリック斑などがみられる場合は、麻疹を疑う必要があります。二峰性の発熱(いったん下がった熱が再び高くなる)があればさらに可能性が高まります。
ただし、医療機関を受診する前に必ず連絡を入れるのが重要です。麻疹は空気感染もあり、待合室でほかの患者さんにうつす危険が非常に高いからです。 - 集団生活の場での注意
学校や職場など、多くの人が集まる場所で一人でも麻疹の発症者が出ると、同じ空間にいた免疫のない人が次々と感染する可能性があります。潜伏期間の人が気づかずに登校・出勤を続けてしまうケースはよくあります。流行が疑われる場合や自分が感染したかもしれないと思う状況では、無理をせず休むことも大切です。
潜伏期間を短縮・延長させる要因
(1) ワクチン接種状況
先述の修飾麻疹でも触れましたが、ワクチンにより部分的な免疫があると、典型的な潜伏期間(10~12日)とは異なるタイミングで発症する場合があります。発疹が出にくく、判断がつきにくいことも多いため、少しでも「あれ?」と感じたら医師の診断を受けましょう。
(2) 免疫力・基礎疾患の有無
免疫力が落ちている状態(たとえば重い基礎疾患がある、あるいはステロイドなど免疫を抑える治療を受けている)だと、潜伏期間がやや短い・あるいは症状が急激に出る可能性も考えられます。一方で、高齢者や妊婦さんでは、発症の仕方が通常と異なることも報告されています。
潜伏期間と感染力のピーク
麻疹の感染力は「発疹が出る前」からすでに非常に強いとされています。具体的には、発疹出現の3~5日前(すなわち、潜伏期間を終えて初期症状が出始めるころ)にはウイルスを排出している可能性が高いのです。
さらに、発疹が消えた後4日間ほども感染力を保持している場合があるため、本人が「もう治った」と思っても、周囲への二次感染リスクが残存します。
このように潜伏期間が長い上、発症初期から空気感染で周囲に広がりやすい点は、麻疹が猛威をふるう大きな理由の一つです。
潜伏期間中の対策:ワクチン接種が唯一の有効予防法
麻疹の潜伏期間そのものを直接「コントロール」するのは極めて難しいですが、発症・重症化そのものを防ぐ最も効果的な手段が「ワクチン接種」です。日本では定期接種として、以下のようなスケジュールが推奨されています。
- 第1期:生後12か月以上24か月未満(1歳前後で1回目)
- 第2期:5歳以上7歳未満で、小学校入学前の1年間(年長児で2回目)
この2回接種で、95%以上の人に予防効果が期待できるとされています。また、子どもの頃に2回の定期接種機会を逃してしまった大人であっても、任意接種という形でワクチンを受けることは可能です。
予防接種の「緊急接種」
万が一、麻疹患者との接触が疑われる場合、72時間以内にワクチンを接種すると発症を阻止、あるいは症状を軽減できる可能性があるとされています。ただし効果は絶対ではないため、普段から2回の定期接種を完了しておくことが何より重要です。
潜伏期間中に注意すべき合併症・症状
麻疹の最も怖い点は、重い合併症です。潜伏期間後に本格的に症状が出ると、免疫力が低下し、二次感染や重症化リスクが上昇します。代表的な合併症は以下のとおりです。
- 肺炎
麻疹合併症の中で最も頻度が高い。ウイルス性、細菌性など複数パターンがある。 - 脳炎
麻疹患者1,000人に1人程度と報告されるが、後遺症や死亡リスクが高く、注意が必要。 - 中耳炎、クループ
小児に多く見られ、呼吸困難につながるケースもある。 - 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)
罹患後5~10年ほどしてから発症し、極めて稀ながら致命的。
潜伏期間後に一気に発症する麻疹の症状は、最初は普通のかぜにも似ているため、早期発見が遅れると合併症リスクを高めます。
妊婦さんや免疫不全の方は特に注意
- 妊婦さん
妊娠中に麻疹にかかると、高熱や重症化はもちろん、流産や早産の可能性も否定できません。ワクチンは生ワクチンであるため、妊娠中は接種ができないことにご留意ください。妊娠前に接種歴が不十分であれば、パートナーや同居家族がしっかりとワクチンを接種しておくことで妊婦さんを守ることができます。 - 免疫不全の方・基礎疾患のある方
ステロイドや免疫抑制剤を使用している方、先天的に免疫機能が弱い方などは、麻疹に罹患すると重症化しやすい傾向があります。潜伏期間中に発熱や咳などの初期症状が出始めたら、早めにかかりつけの医師へ相談しましょう。
医療機関受診時のお願い
もしも自分や家族に発熱やコプリック斑、全身発疹などの麻疹が疑われる症状が出た場合、必ず医療機関に事前連絡の上で受診するようにしましょう。麻疹患者が待合室で周囲にウイルスを広げる可能性が非常に高いためです。受診の際に以下の情報を伝えるとスムーズです。
- 症状の具体的内容(発熱の程度や咳・鼻水の有無、発疹が出始めた場所とタイミングなど)
- ワクチン接種歴(いつ接種したか、回数など)
- 麻疹患者との接触歴や海外渡航歴の有無
潜伏期間を踏まえた日頃からのセルフチェック
- カレンダーや手帳に接触歴や体調をメモ
「いつ、どこで麻疹患者と同じ空間にいたかもしれない」「10日後から2週間ぐらいは要注意」というように、潜伏期間の目安を把握しておくと早期発見につながります。 - ワクチン接種の記録を確認
小さいころの母子手帳を引っ張り出して、自分が1回しか受けていない場合、2回受けてもかなりの年数が経っている場合には、主治医に相談して抗体価検査や追加接種を検討しましょう。 - 流行情報をチェック
地域での麻疹流行状況や、海外渡航が予定されている場合は、その渡航先の麻疹流行状況を事前に調べておきましょう。特に留学や長期滞在などで海外に行く場合、日本国内より接種率が低い国・地域で麻疹が流行していることがあります。出発前にワクチン接種を済ませておくと安心です。
まとめ:潜伏期間を知って、早めの対策を
以上のように、麻疹の潜伏期間は7~21日、主に10~12日が多いとされ、そのあいだに周囲への感染リスクを抱えながら日常生活を送ってしまうことが、麻疹流行の大きな要因のひとつです。感染力は非常に強く、空気感染まで起こるため、集団生活の場では一気に広がってしまう恐れがあります。
しかし、麻疹には特効薬がなくとも、ワクチン(MRワクチン)という強力な予防手段があるのが救いです。日本では1歳前後と小学校入学前の2回接種が基本ですが、それを逃した大人も含め、「いま自分がどのくらい免疫を持っているのか」を知っておくことが大切です。必要に応じて追加接種を受けることで、重症化や合併症のリスクを大幅に下げることができます。
日頃から、
- ワクチン接種歴の確認
- 流行時期や海外渡航時の早めの対策
- 発熱・かぜ症状などがあったら早めに医療機関へ相談(事前連絡を忘れずに)
といったポイントを意識しておくと、いざというとき冷静に対処しやすくなるでしょう。もし麻疹が疑われる症状や、患者さんとの接触機会があった場合は、潜伏期間の可能性がある10日前後は特に体調に注意を払い、周囲への感染拡大を防ぐよう配慮しましょう。
今回はこの辺で。また次のブログでお会いしましょう。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック
院長:小野渉