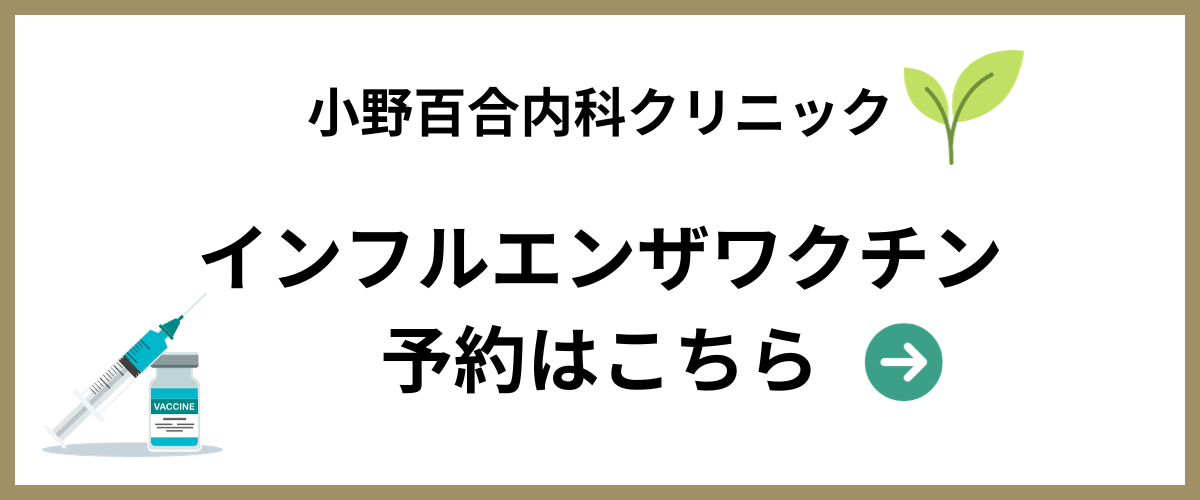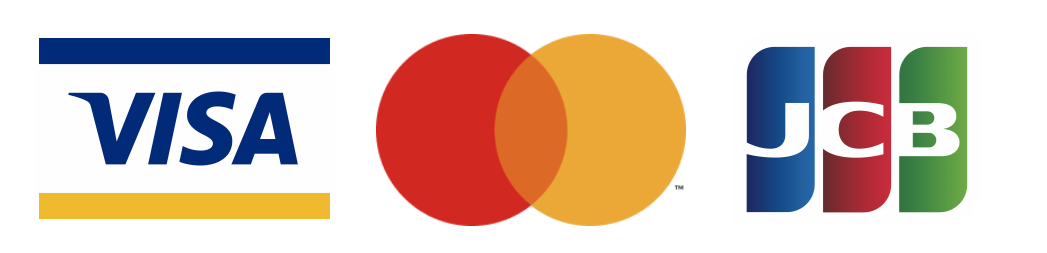札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。2025年7月に改訂予定の「高血圧管理・治療ガイドライン2025(JSH2025)」の草案が、第46回日本高血圧学会総会で発表されました。前回の2019年版から6年ぶりの見直しとなる今回は、ガイドラインの名称も「治療」から「管理・治療」へと変更され、単なる薬物治療ではなく、生活習慣の改善や行動変容を含めた包括的な管理を目指す方向性が明確に打ち出されています。本記事では、JSH2025のポイントを内科医の目線からわかりやすく解説します。このブログを読んでガイドラインの変更点や最新の治療目標への理解が深まれば幸いです。
目次
高血圧の基準と治療目標は維持、しかしアプローチは進化
JSH2025では、これまで通り高血圧の基準を「140/90mmHg以上」、75歳未満の合併症のない患者における降圧目標を「130/80mmHg未満」とする方針を維持しています。欧米ではより厳しい降圧目標への動きも見られますが、日本では高齢化や地域医療体制を考慮し、現実的かつ実行可能な基準を重視する形です。ただし、基準値を満たさない「正常高値(130〜139/80〜89mmHg)」の人々についても早期介入が必要であることが明確に記載されており、これまで以上に予防的な視点が加わっています。
薬物治療はステップ制で整理、ARNIやMRAの位置づけも明確に
治療に用いる降圧薬は、主要薬剤(グループI)と補助薬剤(グループII)に分類され、治療ステップも3段階に整理されました。まずは長時間作用型のカルシウム拮抗薬(CCB)、ARB、ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬の中から単剤治療を行い、目標血圧に到達しなければ速やかに併用療法へ移行します。注目のARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)やMRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)は、特定の病態に応じて第二段階以降に追加が検討される「グループII」として記載され、心不全や慢性腎臓病における活用が期待されます。
生活習慣改善への介入も強化、アプリや尿中ナトカリ比を活用
JSH2025では、生活習慣の改善にも重点が置かれており、減塩目標はJSH2019同様に「1日6g未満」とされています。新たに「尿中ナトリウム/カリウム比」の測定と活用が推奨されており、スマートフォンアプリや専用測定デバイスを通じて患者の自律的な健康管理を促す仕組みも提案されています。これにより、行動科学に基づいた「行動変容」支援が現場レベルで進むことが期待されています。
高齢者・女性・がんサバイバーにも対応、パーソナライズド医療へ
JSH2025では、従来の年齢ベースから病態ベースの管理にシフトしています。特に高齢者に対しては、フレイル(虚弱)や終末期ケアの観点を取り入れた個別対応が重視され、より柔軟な治療戦略が求められています。また、妊娠・更年期といった女性特有の病態、がん治療後の「オンコ・ハイパーテンション(がん関連高血圧)」などへの対応も盛り込まれ、より包括的な医療提供が可能となる設計です。

まとめ:
JSH2025は、高血圧を単なる「病気の数値管理」から「生活全体を見直す健康管理」へと昇華させた新しいガイドラインです。治療の選択肢が広がるだけでなく、患者の行動や意識に寄り添う構成となっており、医療者にとっても日常診療を再設計する良い機会となるでしょう。
当院では高血圧を含めた生活習慣病外来を実施しております。ご興味のある方はこちらからご連絡ください。
今回はこの辺で。また次のブログでお会いしましょう。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック