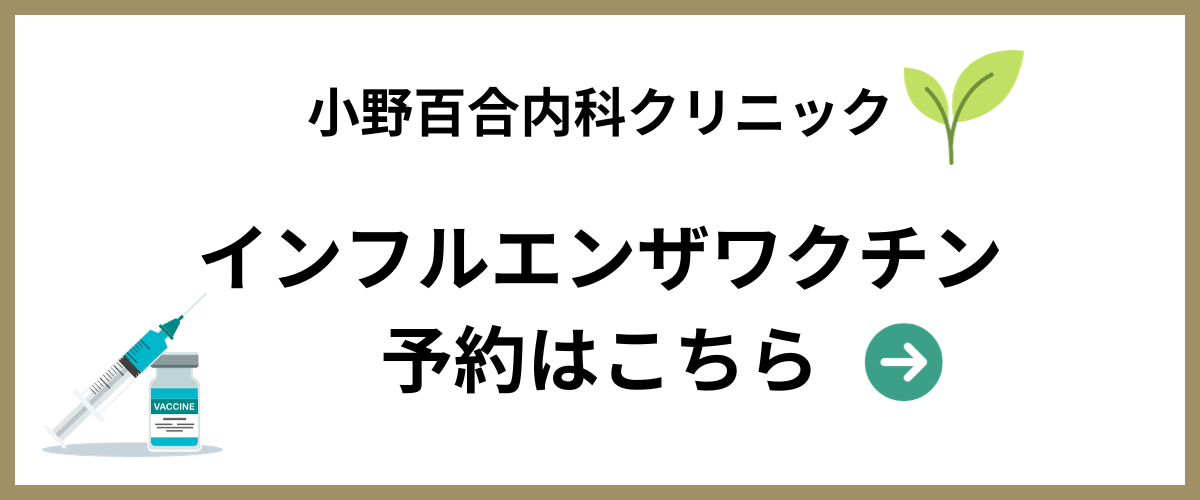札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。みなさんは糖尿病と歯周病の関係はご存知でしょうか。糖尿病が悪くなると歯周病が悪くなると聞いたことがある方も多いと思います。今回はそんな糖尿病と歯周病の関係について糖尿病内科医の目線から解説しようと思います。この文章を読んで歯周病についての理解を深めていただければ幸いです。
糖尿病と歯周病の関係とは?
糖尿病と歯周病にはとても深い関係があり、糖尿病の合併症の第6番目にあげられています。そしてその関係性から、糖尿病の状態=歯周病の状態というように双方が連動した関係性にあります。コインでいう、表裏一体の状態です。
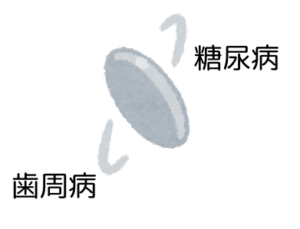
例えば、糖尿病患者さんがインフルエンザや肺炎、膀胱炎などにかかり、発熱すると、急激に血糖値が上がります。これは炎症細胞から分泌される物質が、血糖を下げることができる、「インスリン」というホルモンの効きを悪くさせてしまうからです。歯周病の炎症は、インフルエンザや肺炎に比べれば、大したことはないと思われるかもしれませんが、一時的なものではなく慢性的で、長期に渡ってじわじわと少しずつインスリンの効きを悪くさせ、糖を分解する効率を悪くし、血糖値が高くなり、糖尿病を悪化させてしまう危険性があります。

一時的な感染症よりも、歯周病のような目立った症状のない慢性感染症の方が、サイレントキラーと呼ばれ、とても怖いのです。また、歯周病により歯茎から出血があると、歯茎の血管から歯周病菌が入り込み、全身に行き渡ってしまいます。血管に入った歯周病菌は体の免疫力で死滅しますが、歯周病菌の死骸の持つ毒素は残り、血糖値に悪影響を及ぼします。このように血糖値に影響を及ぼす歯周病とは、どのような病気なのでしょうか?
〈歯周病ってどんな病気?〉
歯周病とは、歯垢=細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯の周りの歯茎に炎症を起こし、歯を支える骨が溶けていってしまう病気です。歯周病は日本人の8割が罹患しているといわれており、年代別にみると30代~60代にかけて多く、30代以上では3人に2人は症状が出ていると言われています。歯周病はゆっくり進行していく病気なので、自分では罹っていることに気づきにくく、症状が出て気づいた頃には、だいぶ病気が進行してしまっている場合があります。自分は症状もないし大丈夫!と思わないで、まずは、チェックリストで歯周病の傾向が出ていないか、確認していきましょう!

〈歯周病セルフチェックリスト〉
こんな症状ありませんか?
□ 口臭が気になる
□ 朝起きたときに、口の中がネバネバする
□ 歯がグラグラする
□ 歯磨きの時に出血する
□ 硬い物が噛みにくい
□ 歯茎が時々腫れる
□ 歯茎が下がって、歯と歯の間に隙間ができてきた
□ 糖尿病がある
※一つでも当てはまれば、歯周病の可能性があります。
歯周病はお口の中だけの症状にとどまらず、全身に及ぼす影響がとても大きい病気です!糖尿病の人はそうでない人に比べて、歯周病にかかっている人が多いという報告が複数あげられています。
〈歯周病の改善方法とは?〉
歯周病は進行を止めることはできても、元の状態には戻せませんので、今の状態よりも悪くならないようにしていくことが大切です。歯周病の原因は、歯垢=細菌でしたが、その栄養源は血液です。ということは出血している歯茎には、細菌=歯周病菌が寄ってきていつまで経っても、歯周病は良い状態に改善しません。炎症のない出血しない歯茎にするには、歯石除去などの歯科医院でのプロフェッショナルケアを受け、自身によるセルフケアにより、歯垢を溜めておかないことが、改善のカギとなります。

〈治療による相乗効果〉
歯周病の適正な治療を歯科医院で受け、病態を落ち着かせることで、血糖値への影響は少なくなり、糖尿病の状態も落ち着くといった、相互関係があります。また、高血糖状態では唾液が減り、お口の中が乾燥して自浄作用が低下したり、唾液中の糖分が多くなると、組織の修復力が低下してしまうことから、血糖コントロールが上手くいっていない場合には、歯周病も悪化しやすくなります。このように歯周病と糖尿病には深い関係があるため、歯科医院受診の際には、糖尿病手帳とお薬手帳を必ずお出しいただき、糖尿病の状況をお伝えいただくことが大切です。
今回はこの辺で。また次のブログでお会いしましょう。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック