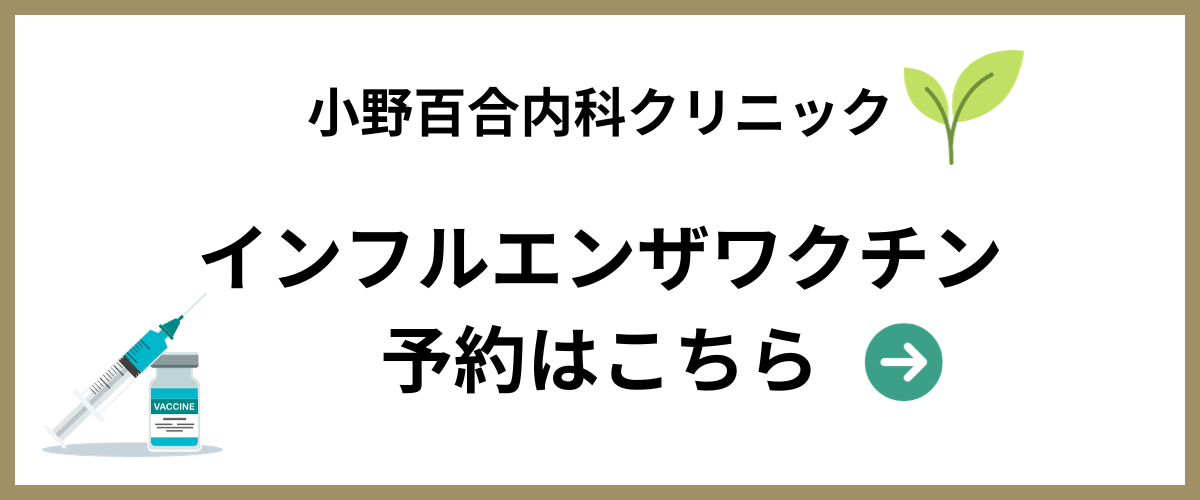札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。みなさんはネバネバした納豆はお好きですか??糖尿病と診断された方や血糖値が気になる方の中には、「納豆って食べても大丈夫?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?結論から言えば、納豆は糖尿病の方にもおすすめできる健康食品です。ただし、いくつかの注意点を押さえた上で、正しい食べ方を心がけることが大切です。記事では、納豆が糖尿病に与える健康効果や、血糖値への影響、食べ方の工夫まで、糖尿病内科医の目線からエビデンスを交えて詳しく解説します。
目次
納豆は糖尿病の人にも適した食品です
納豆は日本の伝統的な発酵食品であり、低GI・低カロリー・高栄養という三拍子が揃った食品です。
納豆100gあたりのGI値は30、1パック(約50g)のカロリーはおよそ90〜100kcalと、血糖値が気になる方にとって理想的な食品です。
納豆に含まれる代表的な健康成分とその効果は以下の通りです。
| 成分 | 主な効果 |
|---|---|
| 植物性タンパク質 | 血糖値の上昇を抑え、筋肉量維持でインスリン感受性を改善 |
| 大豆イソフラボン | 耐糖能異常の改善、動脈硬化予防、女性の更年期対策 |
| 水溶性食物繊維 | 糖質の吸収速度を遅らせ、血糖値の急上昇を防ぐ |
| ナットウキナーゼ | 血栓を予防し、脳梗塞や心筋梗塞などの合併症リスクを軽減 |
| 発酵による腸内環境改善 | 慢性炎症を抑制し、インスリン作用の改善に貢献 |
科学的にも裏付けられた納豆の効果
大豆イソフラボンで血糖コントロールを改善
国内外の研究で、大豆食品の摂取が糖尿病や心血管疾患リスクの低下に寄与することが確認されています。例えば、BMJやNutrientsなどに掲載されたメタアナリシスでは、納豆や味噌などの発酵性大豆食品をよく食べる人は、2型糖尿病や脳卒中、心筋梗塞のリスクが低いとされています。

ナットウキナーゼの血栓予防作用
ナットウキナーゼは納豆のネバネバに含まれる酵素で、血栓の元であるフィブリンを分解する作用を持ちます。
糖尿病の方は血管が傷みやすく血栓リスクが高まるため、ナットウキナーゼの働きは大きなメリットになります。
糖尿病の方が納豆を食べる際の3つの注意点
-
ワルファリン服用中は注意
納豆にはビタミンKが多く含まれ、ワルファリン(商品名ワーファリン)の効果を打ち消してしまうため、服用中の方は納豆を避けるか医師に相談しましょう。 -
過剰摂取は避ける
1日1パックが適量です。納豆の過剰摂取は、大豆イソフラボンの摂取過多やプリン体による尿酸値上昇、納豆菌の過剰繁殖による消化器不調を招く可能性があります。 -
白米と一緒に食べすぎない
納豆ご飯の組み合わせは人気ですが、白米は高GI食品。量に気をつけるとともに、ごはんが熱すぎるとナットウキナーゼの効果が失われるため、別の器にするかご飯を少し冷ましてから食べましょう。
納豆の効果を最大限に引き出す3つの食べ方
-
加熱せずに食べる
ナットウキナーゼは50℃以上で失活するため、納豆チャーハンなどの加熱調理は避けましょう。 -
継続して食べる
腸内環境改善や血糖コントロールには継続的な摂取が重要。朝食で代謝を高める、夕食で血栓予防など、自分の生活スタイルに合わせて取り入れましょう。 -
他の食材と組み合わせる
キムチ(乳酸菌)、チーズ(ビタミンA)、お酢(酢酸)、ネギやニラ(アリシン)などと組み合わせると、腸活や血糖コントロールの相乗効果が期待できます。

研究でも裏付けられた納豆の持つ可能性
国立がん研究センターの「JPHC研究」では、納豆をよく食べる人は心筋梗塞や脳卒中の死亡リスクが20%以上低下することが報告されました。また、最近では大阪公立大学の研究により、納豆菌が自然免疫やインスリン様成長因子経路に作用し寿命を延ばす効果がある可能性も指摘されています。

まとめ:納豆は糖尿病食に取り入れたい「最強の発酵食品」
納豆は、糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満、さらには認知症の予防にも役立つ可能性のある多機能な発酵食品です。ただし、薬との相互作用や過剰摂取には注意が必要です。1日1パックを目安に、熱を加えずに、他の発酵食品や野菜と組み合わせて、血糖値コントロールと健康寿命の延伸に役立てましょう。
最後に糖尿病の方にも安心して楽しめる納豆を使ったレシピを、血糖値の急激な上昇を抑える・食物繊維やたんぱく質を補えるなどの視点から、複数ご紹介します。どれも簡単で美味しく、日常の食事に取り入れやすいレシピです。