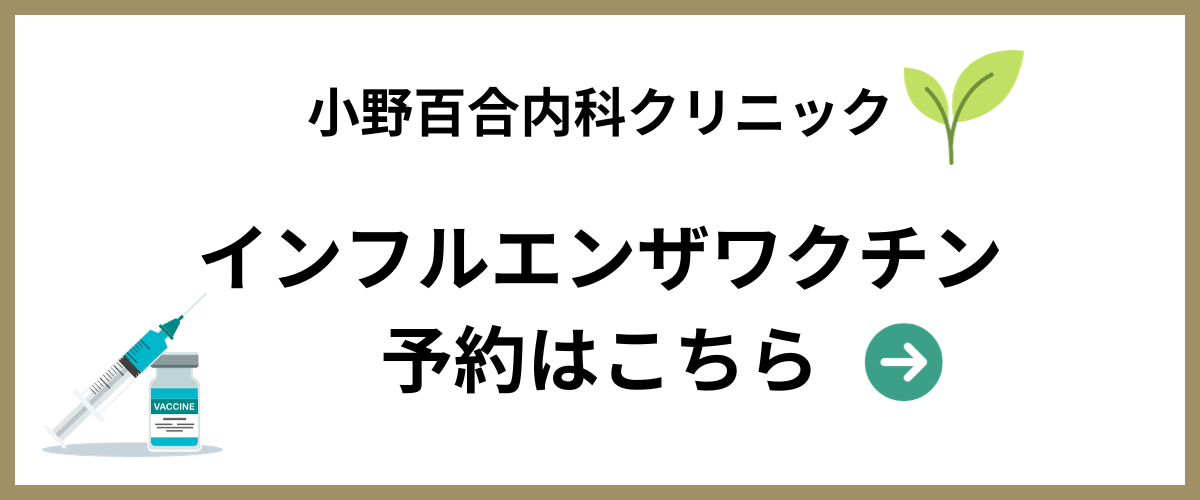札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。2025年4月、タイ・バンコクで開催された国際糖尿病連合(IDF)の世界糖尿病会議にて、新たな糖尿病の分類「5型糖尿病(Type 5 Diabetes)」が公式に認定されました。この発表は、世界中の糖尿病診療と公衆衛生政策に大きな影響を与える可能性があります。そんな5型糖尿病に関して糖尿病内科医の目線からわかりやすく解説してみようと思います。ぜひご一読ください。
5型糖尿病とは?
5型糖尿病は、長期的な栄養不足によって膵臓の発達が妨げられ、インスリンの分泌能力が著しく低下する糖尿病です。特に小児期や思春期の栄養不良が原因となることが多く、これまで1型や2型糖尿病と誤って診断されていたケースも少なくありません。
この病態は、**SIDD(Severe Insulin-Deficient Diabetes:重度インスリン欠乏性糖尿病)**として知られ、アジアやアフリカなどの低・中所得国を中心に、全世界で2,000万〜2,500万人が罹患していると推定されています。

1型・2型糖尿病との違い
| 項目 | 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | 5型糖尿病 |
|---|---|---|---|
| 主な発症要因 | 自己免疫反応 | インスリン抵抗性、生活習慣 | 小児期の栄養不足 |
| 発症年齢 | 小児〜若年〜高齢 | 中高年以降が多い | 小児期〜若年 |
| 体型 | 痩せ型が多い | 肥満傾向が多い | 痩せ型 |
| インスリン治療 | 必須 | 場合により必要 | 一部を除き、経口薬で対応可能 |
| インスリン抵抗性 | なし | あり | なし |
| 誤診されやすい型 | ― | ― | 1型または2型 |
なぜ今「5型糖尿病」が認定されたのか?
5型糖尿病に該当する病態は、70年以上前から貧困地域で観察されていたものの、明確な診断基準がなく、1型や2型として処理されてきました。
しかし近年、米国アルバート・アインシュタイン医科大学のMeredith Hawkins教授や、インドのNihal Thomas教授らによる研究により、独特な代謝プロファイルが明らかになりました。その結果、他の型とは本質的に異なる疾患であると認識され、今回の国際的な分類に至ったのです。

日本ではどうなる?
現時点では、日本糖尿病学会(JDS)やアメリカ糖尿病学会(ADA)は、「5型糖尿病」を正式な診断名として採用していません。しかし、高齢者や摂食障害患者において、栄養不足と糖代謝異常が関与する病態が注目されつつあり、今後の議論の進展が期待されています。
なぜこの認定が重要なのか?
-
適切な治療の提供:インスリン療法が逆効果となる場合もある5型糖尿病では、誤診を避けることが生命に直結します。
-
費用対効果の高い治療:低所得国ではインスリンの確保が困難な場合も多く、経口薬での管理可能性は大きな意義を持ちます。
-
国際的支援の強化:IDFは今後、5型糖尿病に関する診断基準の策定、医療従事者への教育、研究レジストリの整備を進めていくとしています。
医療現場で求められる視点の変化
これまでの「糖尿病=過栄養」といったイメージから、「栄養不良による糖尿病」という新たな概念への理解が求められています。食事療法や治療方針も、患者の栄養背景を含めた個別対応が一層重要になるでしょう。
まとめ
-
**「5型糖尿病」**は、長期的な栄養不足により膵臓の発育が妨げられ、重度のインスリン欠乏をきたす糖尿病です。
-
IDFが2025年に公式認定し、今後国際的な研究と診療体制の整備が進みます。
-
日本ではまだ正式な診断名ではありませんが、今後の動向に注視が必要です。
-
栄養状態と糖尿病の関係に、より深い理解が求められる時代に入っています。
当院では、患者さん一人ひとりの背景に合わせた糖尿病診療を心がけています。ご自身やご家族の糖代謝、栄養状態に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック
院長 小野渉