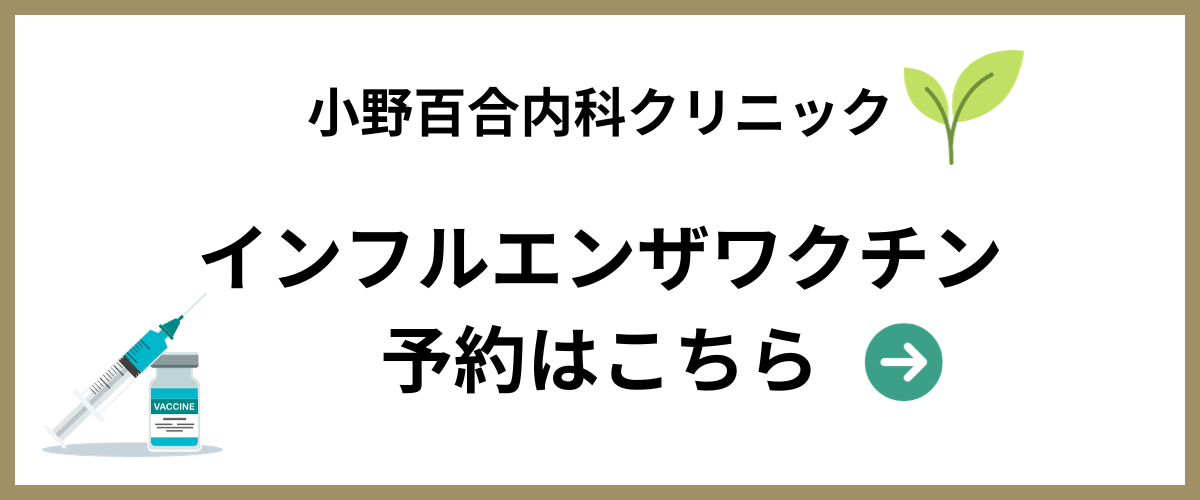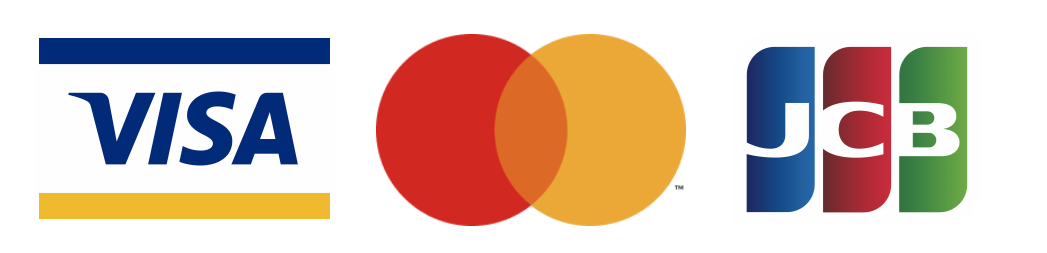札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。2025年4月14日、京都大学医学部附属病院は会見を開き、1型糖尿病の患者さんに対して、iPS細胞から作製したインスリン分泌細胞(膵島細胞)を移植する治験を開始したと発表しました。今年2月に1例目の患者さんへの移植手術を実施し、経過は良好とのことです。今後2例目、3例目へと段階的に手術を進め、安全性と有効性を確認した上で2030年代の実用化を目指すとしています。
1型糖尿病は、免疫の異常などによってインスリンを作り出す膵β細胞が破壊される疾患で、国内には12万~14万人ほどの患者さんがいると推定されます。そのうち10%ほどは血糖変動が激しい「ブリットル型」と呼ばれるタイプで、低血糖を自覚できないまま重症化するリスクが高いことが課題です。
インスリン注射は血糖値管理に欠かせない重要な治療ですが、毎日の注射は生活の制約になりうるため、根本的な新しい治療法が世界中で期待されています。

目次
そもそも1型糖尿病とは? なぜインスリン分泌細胞が必要なのか
1型糖尿病では、自己免疫反応などによって膵臓のランゲルハンス島にあるインスリン分泌細胞(膵β細胞)が壊され、血中インスリンが不足してしまいます。インスリンは血糖値を下げる作用を持つホルモンのため、膵β細胞が働かない1型糖尿病の患者さんは、インスリン注射やインスリンポンプなどによる補充が欠かせません。
しかし、血糖値のコントロールが非常に難しいケースも多く、血糖値が極端に上下する「ブリットル型」1型糖尿病では、命にかかわる重症低血糖発作や合併症のリスクが高くなります。
膵島移植とドナー不足の課題
1型糖尿病の治療としては、これまでもドナーから提供された膵臓の中の「膵島細胞」を患者さんに移植する「膵島移植」が行われてきました。2020年に公的医療保険適用となったことで、日本国内でも保険を使って移植を受けることは可能になっています。
しかし、膵臓提供(ドナー)は圧倒的に数が少なく、国内の膵島移植の実施件数は年間わずか数例にとどまっているのが現状です。さらにインスリン注射不要(インスリン離脱)を目指すには複数回の膵島移植が必要になる場合も多く、慢性的なドナー不足を解消するための新たな細胞源が求められてきました。
iPS細胞から作った膵島細胞を移植する治験がスタート
京都大学医学部附属病院の取り組み
そこで注目されているのが、人工的に多能性幹細胞を作り出せる「iPS細胞」から膵島細胞を作製し、患者さんに移植する技術です。山中伸弥教授が2007年にヒトiPS細胞の樹立に成功して以来、さまざまな領域で応用が検討されています。糖尿病領域でも、iPS細胞由来の膵島細胞を移植して血糖値を正常化させる研究が進んでいます。
京都大学医学部附属病院は、
- 健康な第三者由来のiPS細胞から作製した膵島細胞
- これをシート状に加工した製品(OZTx-410)
を使い、1型糖尿病の患者さんの腹部皮下に移植する医師主導治験を行います。2025年1月から治験を本格的に開始し、まず3人の患者さんを対象に安全性を確認します。患者さんが移植を受ける際は、拒絶反応を抑えるための免疫抑制剤を併用しながら、移植後5年間にわたり定期的に経過観察を実施する計画です。
2025年2月には1例目の移植開始を予定していましたが、今回2025年2月に移植が実施され、その後公表された結果では「大きな問題なく経過は良好」との報告がありました。現段階では安全性が確認され、インスリン分泌能に関しても一定の効果が見られ始めているといいます。

今回の治験のポイント
- 適応となる患者さん
内因性インスリン(膵β細胞由来のインスリン)分泌がほぼ廃絶しており、血糖管理が著しく困難な1型糖尿病患者さん(膵島移植の適応基準を満たす方)。 - 移植方法
全身麻酔下で、シート状のiPS細胞由来膵島細胞を腹部皮下に移植。
移植後は免疫抑制剤を継続的に服用し、5年間は安全性や効果の評価を行う。 - 治験のゴール
安全性を確認するとともに、有効性(インスリン分泌能の改善、血糖コントロールの安定化など)を検証し、2030年代の実用化を目指す。
中国で報告された「自家由来iPS細胞」での臨床研究成功例
実は海外でも、同様の取り組みが進められています。2023年には、中国・北京大学や南開大学などの研究グループが「患者さん自身の細胞から作り出したiPS細胞由来の膵島細胞を移植し、1型糖尿病の治療に成功した」事例を医学誌『Cell』に報告しました。
中国の事例の概要
- 対象患者さん:25歳の女性で、11年間1型糖尿病を患っていた。
- 治療法:患者さん自身の細胞を化合物で初期化した「化学的に誘導したiPS細胞(CiPSC)」を作り、それを膵島細胞へ分化させて腹部の前腹直筋鞘下に移植した。
- 結果:移植後およそ2ヵ月半(75日後)からインスリン注射が不要となり、以後1年以上、血糖値はほぼ目標範囲内で安定。
- 安全性:1年間の追跡では、腫瘍化などの重大な合併症は認められなかった。
ただしこの研究はまだ1人の患者さんでの成功例であり、多くの患者さんに適用して同様の成果が得られるのかについては、今後さらに検証が必要とされています。また、1型糖尿病の場合は自己免疫による膵島破壊が原因のため、厳密には「本人由来の細胞」でも免疫寛容がどの程度得られるかは慎重に見極めが必要です。
とはいえ、この症例は「iPS細胞由来の膵島細胞移植が、理論上はインスリン注射からの解放をもたらしうる」ことを示した重要な第一歩といえます。
今後の展望:ドナー不足を解消し、新たな治療オプションに
1型糖尿病に対する膵島移植が2020年に保険収載されたとはいえ、ドナー臓器不足が根本的な制約となっています。iPS細胞を使う方法は、こうしたドナー不足を解消できる可能性がある大きなブレイクスルーです。また、患者さん自身の細胞を使う“自家移植”が実現すれば、拒絶反応や免疫抑制剤の問題を軽減できる将来像も期待されます。
課題とリスク
一方で、腫瘍化リスクや長期的な安全性の評価、作製コスト、製造プロセスの安定化など、課題は少なくありません。実用化を目指すには、以下のようなポイントをクリアしていく必要があります。
- 大規模臨床試験での有効性・安全性の検証
現在進められている治験はあくまで初期段階です。対象患者数を増やし、長期追跡することで、腫瘍化やその他の副作用リスクを徹底的に調べる必要があります。 - コスト・大量培養の課題
iPS細胞から膵島細胞を安定的に大量培養するための技術基盤やコスト削減は不可欠です。どれだけ優れた治療法でも、実際に臨床に適用できるかどうかは費用面や生産体制に大きく左右されます。 - 免疫抑制と自己免疫の問題
1型糖尿病における自己免疫は、同種移植(他人由来)だけでなく、自家移植でも問題となる可能性があります。免疫抑制剤をどの程度使う必要があるのか、免疫寛容が成立するのかなど、引き続き検討が必要です。
まとめ
- 京都大学医学部附属病院が1型糖尿病患者に対するiPS細胞由来膵島細胞移植の治験を開始。
すでに1例目の患者さんにシート状の膵島細胞を腹部に移植し、経過は良好。さらに2例目、3例目の移植を行い、安全性と有効性を検証して2030年代の実用化を目指す。 - iPS細胞由来の膵島移植は、ドナー不足や複数回移植の課題を解消する可能性。
国内では保険収載された膵島移植ですが、慢性的なドナー不足を背景に年間数例にとどまっている。iPS細胞を利用することで、将来的に患者さんの新たな選択肢になることを期待。 - 海外(中国)の例では、自家iPS細胞を使った患者さんが移植後インスリン離脱を達成。
まだ症例数は限られるものの、移植後の血糖値管理が大幅に改善した報告があり、安全面でも1年間は重大な問題はみられなかった。今後の可能性を示す先行データとして注目される。 - 課題と今後の方向性。
腫瘍化リスクや長期安全性の確認、大量培養の技術的課題、コスト面など解決すべき点はまだ多い。しかし1型糖尿病の根本治療として大きな期待が寄せられており、国内外で研究・開発が活発化している。
今回の治験は“始まりの一歩”
京都大学の矢部教授は「患者さんへの負担を減らし、インスリン注射が不要な社会を実現したい」とコメントしています。すでに1例目の移植では大きなトラブルなく退院できたこと、さらに2030年代の実用化を視野に入れるという報道があり、今後の追加症例や経過報告に注目が集まります。
iPS細胞を使った先端医療は非常に期待される一方で、安全性の確立や費用対効果の検証には慎重な検討が必要です。とはいえ、今回の京都大学の治験開始や海外での成功報告は、1型糖尿病の根治的治療を目指す研究が確実に進展していることを示す大きなニュースといえるでしょう。
いかがだったでしょうか。また次のブログでお会いしましょう。
札幌駅近く、大通り駅近くの小野百合内科クリニック
院長 小野渉
参考リンク・文献
- 京都大学医学部附属病院「iPS由来膵島細胞シート移植に関する医師主導治験の開始について」(2024年10月2日発表)
- 医学誌『Cell』(2023年) 中国における自家iPS細胞由来膵島移植の研究報告
- Nature, Cell など各種海外論文
- 「1型糖尿病の患者数とインスリン依存状態」日本糖尿病学会等